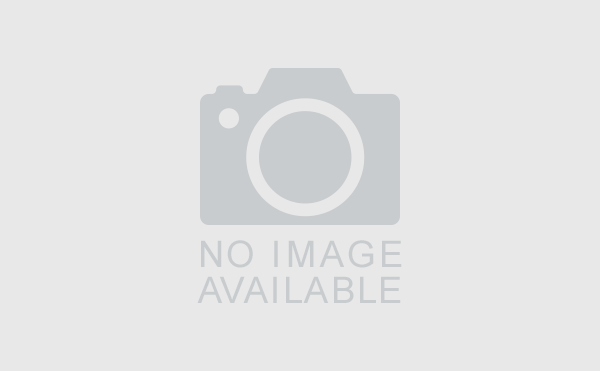Newsletter vol.34 論語と算盤とSDGs⑦ <伊藤忠兵衛>
豊島 敦
2020年に米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏が、日本の5大総合商社(伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事)の株式を保有していることが明らかになった。バブル崩壊後の「失われた30年」を象徴する存在でもあった総合商社への投資は、意外なニュースとして受け止められた。2025年に入り、トランプ政権による保護主義的政策などから世界経済の不安定化が懸念され、世界の株価は乱高下し、日本の商社株もその影響を受ける中、バフェット氏がさらに商社株を買い増していたことが報じられた。日本の総合商社の将来性を信じ、過小評価されていると判断したのだろう。本稿では、5大商社のうち伊藤忠商事と丸紅の創業者である初代・伊藤忠兵衛に焦点を当てる。伊藤忠兵衛が二宮尊徳の報徳思想に直接触れていたという記録はないが、儒教や仏教に基づく江戸時代以来の道徳観を背景に、勤勉と倹約を旨としながら公益と私益の両立を図るという点で、報徳思想と通じるものがある。二宮尊徳が幼少期の苦難を乗り越えて立身出世を遂げたことは明治期には広く知られており、忠兵衛がその思想に共鳴していた可能性も否定できないと思う。
政商三菱、江戸時代から続く豪商三井・住友と異なり、伊藤忠は、江戸末期に個人商店から急成長を遂げた企業である。伊藤忠兵衛は1842年(天保13年)、現在の滋賀県犬神郡豊郷町に近江商人・伊藤長兵衛の次男として生まれた。伊藤家は代々「紅長(べんちょう)」の屋号で、近江特産の繊維品を関西から全国に販売する「持ち下り商い」を行っており、忠兵衛も1858年(安政5年)15歳で商いの道に入った。1872年(明治5年)に本家から独立、大阪で呉服商「紅忠(べんちゅう)」を開業、1885年(明治18年)には海外貿易にも進出している。1918年(大正7年)には伊藤忠商事・伊藤忠商店を設立し、1921年(大正10年)には本家の伊藤長商店と合併して丸紅商店を創設した。
忠兵衛は渋沢栄一や五代友厚が築いた近代日本のインフラを舞台に活躍した商人の一人であったが、近江商人に古くから伝わる「店法」を上手く近代化・構造化させて、組織管理と人材育成を重視していた点が非常に興味深い。店員の義務と権限を定めた「店法」を設け、若い店員にも大きな取引を任せるほか、社内会議制度を導入して意見を反映させるなど、近代的で合理的な経営手法を導入した。特に「採用・昇進・報酬・異動」の明文化や、「能力・成果・忠誠」に基づく昇進制度を採用したことは、現在でも十分に出来ている企業は少ないのではないか。人材育成も、従来の慣行「見て慣れて覚える」ではなく、初代忠兵衛の妻である八重氏が入社研修から一貫して教育を手掛けるなど、現在の人的資本経営に近い感覚で経営を行っていた事が覗える。(尚、この八重氏は、事業・人事担当役員相当の実務を担っており、この時期の女性として大変興味深い活躍をした人物である。)
また、利益を「主人」「奉公人」「将来への備え」に分ける「利益三分主義」を採用。封建的色彩の残る当時において、従業員への利益還元や内部留保の重視は画期的だった。さらに、全店員参加で毎月1と6のつく日にすき焼きパーティーを開く、相撲観戦や納涼舟遊びを行うなど、現代の社内レクリエーションに相当する取り組みも実施していた。当時は、丁稚奉公の慣習が続いており、休みは盆と暮れぐらいという時代である。アメリカでも長らく株主利益至上主義が主流で、従業員などのステークホルダーの利益が重視されるようになったのは2000年代に入ってからである。
忠兵衛は浄土真宗の熱心な信者でもあり、「陰徳善事(人知れず善行を積む)」を大切にしていたという。また、経営哲学として「商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの」という言葉を残している。この考え方が「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の原点となったといわれている。「三方よし」は近江商人の理念として有名だが、実際には明文化された家訓などは存在せず、滋賀大学の小倉教授が忠兵衛の言葉をもとに体系化したものとされる。いずれにせよ、「三方よし」は多様なステークホルダーを重視する日本的経営を象徴する言葉として、多くの企業が経営理念に掲げている。
1990年代、日本の総合商社は「不要論」にさらされていた。バブル崩壊後、不動産や海外事業で巨額の損失を出したことや、製造業の国際化やITの普及によって、企業が商社を介さずに直接情報収集・取引を行えるようになったためである。情報仲介機能や流通機能が不要視され、欧米の投資家からは、同様な事業を営む企業が欧米には無いこともあり、「多角化した総合商社は事業内容が不透明でわかりにくい。経営陣の事業にかかる専門性も活かせず、非効率なのではないか」との指摘があった。当時のバフェット氏はコカ・コーラやマイクロソフトといった「事業内容がわかりやすく、安定した配当を生む企業」への投資を重視しており、日本の総合商社が投資対象になるとは考えにくかった。
奇しくも、バフェット氏が商社株への投資を開始した2020年、伊藤忠商事はCSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)など現代的経営との親和性を背景に、「三方よし」を改めて経営理念として掲げた。同社のホームページでは、「三方よし」の精神が英語の動画でも紹介されており、国際的にもその価値を発信している。「三方よし」は、株主、取引先、従業員といった多様なステークホルダーに配慮しながら企業価値を向上させる「ステークホルダー資本主義」そのものである。バフェット氏は基本的には株主利益を重視する立場にあるが、短期的な利益追求には否定的であり、長期的視点で企業価値を高めるためには、従業員や取引先などの利益も尊重すべきと考えている。伊藤忠兵衛が築いた経営哲学が、160年の時を経て、世界的な投資家から「価値ある経営」として評価されていることは、極めて示唆に富むと考える。



【参考文献等】
有馬敏則「『三方よし』と『陰徳善事』」彦根論叢 No386滋賀大学経済経営研究所
伊藤忠商事「歴史と沿革」https://www.itochu.co.jp/ja/about/history/index.html
丸紅 「丸紅の歴史」 https://www.marubeni.com/jp/company/history/
公益財団法人豊郷済美会 伊藤忠兵衛記念館 https://toyosatosaibikai.or.jp/
豊島 敦 (Toyoshima Atsushi)
株式会社アスカコネクト 顧問
新卒で全国信用金庫連合会(現 信金中央金庫)に入庫、おもに投融資業務に携わる。1997年~2002年ニューヨーク支店にて、北米クレジット投融資、ストラクチャードファイナンス投資などを担当。その後、ニューヨーク駐在員事務所長、名古屋支店長、法人営業推進部長、中小企業金融推進部長を歴任。2021年理事に就任、2024年6月退任。現在は常勤の他、株式会社地域金融研究所 特別顧問、クオンタムリープベンチャーズ株式会社 アドバイザー、 及び Tranzax株式会社 顧問を務める。
W.P. Carey School of Business , MBA