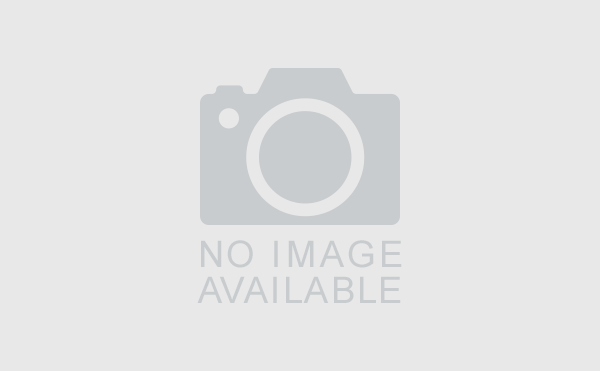Newsletter vol.33 論語と算盤とSDGs⑥ <御木本幸吉>
豊島 敦
2002年世界で初めて、近畿大学は人口孵化によって生まれたクロマグロの稚魚を育成し、再び産卵させる「完全養殖」に成功した。クロマグロの安定供給に貢献する技術として期待されていたが、その完全養殖が事業として岐路にたたされているという。餌代の高騰や、クロマグロの資源量が回復し、完全養殖の算盤勘定があわなくなってしまっているようだ。日本では江戸時代からウナギや海苔の養殖が行われており、現在に至るまでその技術の高さは世界から認められる所であるが、御木本幸吉は明治期に世界で初めて真珠の養殖に成功し、今日まで世界の真珠産業をリードし続ける企業「MIKIMOTO」を創業した人物である。「真珠王」とも称される幸吉も報徳思想の信奉者であり、二宮尊徳の言葉を弟子がまとめた「二宮翁夜話」を7回熟読し、「海の二宮尊徳となる!」と公言していたと伝えられている。今回は、御木本幸吉がどのように報徳思想を昇華させたのか、足跡をたどってみたい。
幸吉は江戸時代末期1858年に、現在の三重県鳥羽市にうどん屋の長男として生まれた。実家はそこそこ手広く商売をしていたが、事業拡大に限界を感じ、家業の傍ら地元の海産物を商うようになる。その後、志摩の天然真珠が輸出用に高値で取引されていることを知ったが、真珠を生み出す「あこや貝」は、当時既に乱獲により絶滅の危機に瀕している状況にあった。荒れた農地を耕作し農村を復興した尊徳のように、あこや貝をよみがえらせ、漁村志摩を豊かにしようと思ったのであろう。真珠養殖という着想を地元の漁業関係者に掛け合ったが、理解を得るどころか、むしろ漁場が荒れるとして強く反対にあったようだ。「二宮翁夜話」でも荒地の開拓など時間がかかる事業は、協力が得られず反対されるものであるから、まずは小さくても結果を出し、理解者、協力者を徐々にふやしていくべきということが語られている。報徳思想で唱えられている「積小為大(せきしょういだい)」は、「小さな努力を積み重ねて大きな成果につなげる」ことであるが、尊徳自身が周囲の理解が得られずに苦労した経験による言葉に幸吉も鼓舞されたことであろう。
20歳で養殖真珠の着想を得て、30歳で研究に着手、35歳で半球形の養殖に成功、そしてついに47歳にして初めて完全な球形の真珠養殖に成功した。その後も真珠を宝飾品の原材料として販売するだけではなく、自社で宝飾品の生産・販売を手掛けるようになる。ジュエリーデザイナーや地金職人をヨーロッパに派遣して技術を習得させ、ダイヤモンド研磨機をベルギーから買いつけ、真珠の生産から宝飾品としての完成品まで一貫生産できる体制を整えた。大正2年のロンドンへの進出を皮切りに、昭和2年にはニューヨーク、翌年にはパリにも進出し、海外での直接販売を実現させている。また、養殖場見学に皇族を招いたり、エジソンと会見して「自分も真珠は発明できなかった」と称賛の言葉を得るなど、ブランド価値を高めるプロモーションも上手い。報徳思想における「勤労」は、単に実直にコツコツ働くこととだけでなく、知恵を働かし、付加価値をつけていくことが奨励されているが、100年以上前にインフルエンサーによるPRでブランド価値を高め、グローバル展開を図っていった幸吉のビジネスセンスは驚かされる。
こうした幸吉の商業的成功の裏側で、中東の湾岸諸国は経済危機に陥った。クウェイト、バーレーンなどペルシャ湾一帯は古来より天然真珠の産地であり、欧州を中心に輸出が行われていたが、養殖真珠が市場を席巻するようになると天然真珠の産業は壊滅した。その結果、クウェイトは石油の採掘権をアメリカの会社に売却、無事石油が発見されたことからクウェイトに繁栄が戻った。しかし、現在は算出量が減りつつあり、石油産業への依存脱却が課題となっている。一方、バーレーンでも石油開発が行われたものの、算出量は多くはなく、早くから産業の多角化に取り組んできた。かつての真珠商人などの館や要塞などの歴史的建造物が今も残されており、天然真珠の産業も復活させた結果、2012年に「真珠採り、島の経済を物語るもの」として世界文化遺産に指定され、現在は観光資源としても活用されている。
さて、幸吉の足跡に戻ろう。早くから世界の市場を得て成功をおさめていたが、第二次世界大戦中には奢侈禁止令により真珠の生産が禁じられた。そこで幸吉は、古来真珠が漢方薬として使われていたことに着目し、真珠やあこや貝を薬品として活用する研究に着手した。結果、戦後には真珠生産の残滓の貝殻や貝肉を利用した化粧品、薬品、健康食品を生産するようになる。転んでもタダでは起きない、むしろそれをバネに出来る幸吉らしいエピソードではあるが、これは現代でいう、不要なものに付加価値をつける「アップサイクル」とも言える。余談であるが、あこや貝から生産されたカルシウムは地元洋菓子店の焼き菓子「シェルレーヌ」にも練り込まれており、現在も大変人気の土産物として有名である。
報徳思想では、余裕のあるものが他者に譲る「推譲」を大切にしているが、これは次世代への投資という意味もある。幸吉は自社の繁栄のみならず、伊勢志摩地域の道路整備や鉄道誘致などにも尽力した。伊勢神宮の内宮と外宮を結ぶ道路は今でも「御木本道路」と呼ばれている。大型観光バスや豪華観光列車で国内外の観光客が来訪するようになった現在の伊勢志摩エリアをみると、御木本幸吉の功績は真珠にとどまらず、郷土の経済的な繁栄という本来の想いが結実し、「海の尊徳」となったといえるのではないか。
【参考文献等】
松沢成文 「教養として知っておきたい二宮尊徳」PHP研究所
Mikimoto 公式サイト https://recruit.mikimoto.com/brand-story.html
飯森富夫 「御木本幸吉の二宮尊徳顕彰」大倉山論集 公益財団法人大倉精神文化研究所
渡邊毅編訳 「現代語抄訳 二宮翁夜話」PHP研究所
世界遺産オンラインガイド https://worldheritagesite.xyz/pearling/
保坂修二「アジア・日本研究Webマガジン クウェート」立命館大学 アジア・日本研究所
豊島 敦 (Toyoshima Atsushi)
株式会社アスカコネクト 顧問
新卒で全国信用金庫連合会(現 信金中央金庫)に入庫、おもに投融資業務に携わる。1997年~2002年ニューヨーク支店にて、北米クレジット投融資、ストラクチャードファイナンス投資などを担当。その後、ニューヨーク駐在員事務所長、名古屋支店長、法人営業推進部長、中小企業金融推進部長を歴任。2021年理事に就任、2024年6月退任。現在は常勤の他、株式会社地域金融研究所 特別顧問、クオンタムリープベンチャーズ株式会社 アドバイザー、 及び Tranzax株式会社 顧問を務める。
W.P. Carey School of Business , MBA