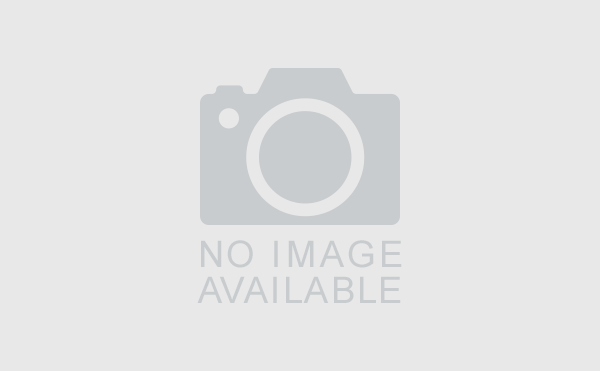Newsletter vol.35 論語と算盤とSDGs⑧ <大原孫三郎>
豊島 敦
「日本初」の西洋美術館と聞いて思い浮かべるのはどこだろうか。有名なところでは国立西洋美術館、そして大原美術館あたりではないだろうか。実は、国立西洋美術館の設立は意外にも遅く1959年(昭和34年)、大原美術館は西洋美術を専門とする美術館としては日本最古の1930年(昭和5年)の設立である。まだ官営の博物館(東京・奈良・京都)ばかりだった時代に、地方の一実業家・大原孫三郎によって設立された稀有な存在である大原美術館は現在でも質の高いコレクションで知られ、2025年4月には「児島虎次郎記念館」も新たに開館した。
「わしの眼には十年先が見える」と語った孫三郎もまた、報徳思想の影響を受けた経営者であり、紡績業の発展に尽くすと同時に、福祉・教育・医療・文化の分野においても幅広い社会貢献を実現した。今回は、先見性と倫理観をもって数多くの持続可能な事業を築いた大原孫三郎について紹介したい。
大原孫三郎は1880年(明治13年)、岡山県倉敷で呉服業、繰綿問屋、米穀問屋、金融業を営む大地主の家の三男として生まれた。父・孝四郎は婿養子として大原家に入り、当時の日本の基幹産業であった紡績業に進出、倉敷紡績(現クラボウ)を創業した。孫三郎は長男・次男が早世したため、幼くして家督を継ぐことが決まり大変甘やかされて育ったという。1897年(明治30年)、16歳で上京し東京専門学校(現・早稲田大学)に進学するが、放蕩の末に巨額の借金をつくり、20歳で故郷に呼び戻された。謹慎生活の中、東京の友人から贈られた『報徳記』をきっかけに、二宮尊徳の報徳思想に出会い感銘を受ける。その後、孤児救済に尽力していたキリスト教徒・石井十次と出会い、聖書研究会に参加し25歳で洗礼を受けている。これ以降、報徳思想とキリスト教の二刀流の思想的支柱が孫三郎の経営哲学に深く根を下ろすこととなる。
1906年(明治36年)、孫三郎は26歳で倉敷紡績の二代目社長に就任する。当時の紡績工場では、貧しい家庭の子女が高温多湿の劣悪な労働環境下で長時間の労働を強いられており、「女工哀史」に象徴されるように労働者の人権が軽視されていた。孫三郎はこれを改革し、寄宿舎や食堂の改善、工場内に診療所や学校を設けるなど、労働者の生活・教育・医療を総合的に支援した。福利厚生費用がかさみ、株主から批判の声が上がると、役員賞与を削減しつつ、利益の三割を配当に充てることにし、株主にも配慮を行った。孫三郎自身が、「人道的教育主義」と呼んだ経営方針はキリスト教的倫理観と報徳思想の「道徳と経済の両立」を体現したものである。
1923年(大正12年)には、倉敷紡績の従業員が1万人近くになったため、診療所を拡充すべく、「東洋一の病院」をスローガンに倉紡中央病院を開設。その後、倉敷中央病院と改名し、従業員以外の地域住民にも門戸を開いた。株主から赤字の病院経営への批判もあったが、孫三郎は「医療が地域経済に利をもたらし、地域経済が潤えば、廻り廻って倉敷紡績の利益にもつながる」と反論。これは報徳思想の「推譲」や、西洋の「ノブレス・オブリージュ」に通じる考えであり、現代のCSR(企業の社会的責任)の先駆けといえよう。現在も倉敷中央病院は公益財団法人として、地域に高水準の医療を提供し続けている。
このように労働環境の改善や地域への貢献に尽力した孫三郎であるが、私が個人的に最も感銘を受けるのは文化事業への貢献、大原美術館の創設である。選ばれた人間だけでなく、誰もが真の美術に触れる事で情緒、感情、人格を養う「人の育成」を目指したのは、孫三郎自身の恵まれた育成環境と現実社会のギャップにあったのかもしれない。
大原美術館創設の背景には、画家・児島虎次郎との友情と芸術への情熱があった。1902年(明治35年)、小島虎次郎は大原奨学会の支援を受け東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学。1908年(明治41年)には孫三郎の援助で渡欧し、ベルギーの美術学校を首席で卒業。1919年(大正8年)には、再び孫三郎の支援でヨーロッパへ渡り、日本の美術教育のために西洋絵画を収集したいと申し出る。虎次郎の「美術は人を育てる」という信念に打たれ、孫三郎は逡巡の末に資金提供を決意。虎次郎は当時すでに人気画家であったモネやマティスら本人と交渉し、優れた作品を買い集めて1921年(大正10年)に帰国した。倉敷の小学校で開催した展覧会は全国から来場者が集まり大盛況となり、西洋美術収集の社会的意義が広く認識された。その後、虎次郎は美術収集のため3度目の渡欧を果たし、エル・グレコなどを持ち帰るが、1929年(昭和4年)、虎次郎は47歳で急逝してしまう。孫三郎はその志を継ぎ、収集した作品や虎次郎の作品を展示する美術館を建設。それが大原美術館である。後を継いだ息子・大原総一郎は、エコール・ド・パリ、日本近代美術、民藝運動関連の作品などを加え、同館を発展させた。孫三郎の存命中は、太平洋戦争などもあり来館者は思うように伸びず、「美術館は事業としては失敗だった」と語っていたというが、今では倉敷のランドマークとなり、国内外から多くの来館者を集めている。フィランソロピーや企業メセナ(文化芸術支援)という言葉もなかった時代の孫三郎の先見の明は敬服に値する。
孫三郎の業績は他にも多岐にわたる。クラレの前身となるレーヨン製造、中国電力の源流である発電事業、昭和初期の金融恐慌時に岡山県内の銀行を統合して誕生した中国銀行、石井十次の孤児院を継承した社会福祉法人・石井記念愛染園など、孫三郎の築いた事業の多くが今も持続的に経営されている。
儒教的価値観を背景とした報徳思想と、キリスト教的倫理観は一見異質に感じるかもしれないが、勤勉や節制といった価値観が経済的成功につながるという点で両者は共鳴していた。報徳思想の「推譲」と、キリスト教の「隣人愛」「責任倫理」はともに、富や権力を持つ者が社会的責任を果たすという点でも一致する。また、労働者を単なるコストとみなし、資本家が労働階級から搾取するという時代に、目先の利益にとらわれず、人財に投資をすることによって、投資額以上の長期的リターンを得ようとする孫三郎の考え方は、現代の「人的資本経営」の先駆けともいえよう。資本家でありキリスト教徒でもあった孫三郎にとって、「論語と算盤」を両立させる報徳思想は、自らの信念に従い、経済的合理性を保ちながら持続的な経営を実践するための羅針盤であった。孫三郎の理念と行動は、十年先どころか、百年先を見通していたと言えるだろう。振り返って今、我々は十年先、百年先に誇れる経営や社会貢献が実践出来ているのか、今一度襟を正したい。

【参考文献等】
・長谷川 直哉 「明治期企業家の経済思想と道徳的深層の関係について」
日本経営倫理学会誌第16号(2009年)
・長谷川 直哉「企業の社会的責任:日本型CSRの源流:大原孫三郎と金原明善」
法政大学イノベーション・マネジメント研究センター ワーキングペーパーシリーズNo127
・兼田 麗子 「大原孫三郎の社会文化貢献」
公益財団法人大倉精神文化研究所 大倉山論集 第63号 平成29年
・兼田 麗子 「留岡幸助と大原孫三郎の社会思想 : 日本近代化過程における社会改良実践の一考察」
早稲田大学リポジトリ 2009年3月10日公開
・クラボウHP 大原孫三郎人物伝 https://www.kurabo.co.jp/sogyo/
・大原美術館HP 美術館の歴史 https://www.ohara.or.jp/history/
豊島 敦 (Toyoshima Atsushi)
株式会社アスカコネクト 顧問
新卒で全国信用金庫連合会(現 信金中央金庫)に入庫、おもに投融資業務に携わる。1997年~2002年ニューヨーク支店にて、北米クレジット投融資、ストラクチャードファイナンス投資などを担当。その後、ニューヨーク駐在員事務所長、名古屋支店長、法人営業推進部長、中小企業金融推進部長を歴任。2021年理事に就任、2024年6月退任。現在は常勤の他、株式会社地域金融研究所 特別顧問、クオンタムリープベンチャーズ株式会社 アドバイザー、 及び Tranzax株式会社 顧問を務める。
W.P. Carey School of Business , MBA